リーダーに必要なのは「正解を知っていること」ではありません。
むしろ、正解がない中で“考え抜く力”を持つことです。
現場では常に曖昧な問題が降りかかります。
「部下のモチベが上がらない」「会議が空回りする」「上司の方針が変わる」──
こうした“答えのない問い”に直面したとき、
多くのリーダーがつい「誰かの答え」を探そうとします。
しかし、その瞬間に“思考停止リーダー”の道が始まるのです。
そんなリーダーにこそ読んでほしいのが、
📘佐々木裕子氏の著書『実践型クリティカルシンキング』。
この本では、「考えるとは、問いを立て直すこと」だと語られています。
正解を探すのではなく、問いを深めていく──
それこそが、曖昧な状況で判断を導くための思考の筋力なのです。
今の時代、過去の成功法則がそのまま通用することはほとんどありません。
求められているのは、情報を鵜呑みにせず、自分の頭で整理し、判断し、
チームにとって最善の道を導き出す力。
──それこそが「クリティカルシンキング(批判的思考)」です。
本記事では、新人リーダーが陥りやすい“思考停止の罠”を紐解きながら、
クリティカルシンキングを実践に落とし込むための第一歩をお伝えします。
第1章:なぜ新人リーダーは“思考停止”に陥るのか
リーダーになった瞬間、多くの人が抱えるのが「考える余裕のなさ」です。
メンバーのフォロー、上司への報告、数字管理、会議準備──
気づけば“自分の頭で考える”時間はどこにも残っていない。
その結果、「とりあえず」「前例通り」「上司の言う通り」という選択が増え、
思考が止まってしまうのです。
けれど、それは決して“能力が低いから”ではありません。
① 情報に埋もれる
毎日、上司・メンバー・他部署からの情報が次々と入ってくる。
その中で「何が重要なのか」を見極める前に動き出してしまい、
結果的に“反応的な行動”ばかりになる。
「言われたから」「必要だと思ったから」で動くうちに、
自分の判断軸を見失っていくのです。
② 構造を整理できない
目の前の課題を“点”で捉えてしまい、
全体像(構造)として考えられない状態。
たとえば「会議がうまくいかない」とき、
「進行が下手だから」と表面的に処理してしまう。
しかし本当の要因は、目的不明・役割不明・事前準備不足など
“構造の欠如”にあるケースが多いのです。
③ 感情に支配される
「部下に嫌われたくない」「上司に早く答えを出したい」──
そんな感情が先行すると、冷静な思考が止まります。
焦りや恐れは、判断を短絡的にし、“考える前に動く”を生みます。
思考停止とは、何も考えていない状態ではなく、
「考えられない状態に追い込まれている」 こと。
ここを自覚できるかどうかが、リーダーとしての分岐点になります。
次章では、「ではどうすれば“考える力”を取り戻せるのか?」──
その鍵となる「クリティカルシンキング」の本質を掘り下げていきます。
第2章:クリティカルシンキングとは何か──単なる分析ではない
「クリティカルシンキング」と聞くと、
“ロジカルシンキングの上位版”や“分析力の強化法”のように思われがちです。
けれど本質はもっとシンプルで、もっと深い。
それは「考え方の質を高めるための姿勢」そのものです。
『実践型クリティカルシンキング』(佐々木裕子著)では、
「考えるとは決めること」という視点を強調しています。
“本当に正しい問いを立てること”こそが、思考の出発点なのです。
「問い」を立て直すことが、思考の再起動スイッチ
リーダーが思考停止に陥る理由の多くは、
“問いが浅い”ことにあります。
たとえば、チームの成果が上がらないとき。
「どうすれば成果を上げられるか?」と考えるのは自然ですが、
クリティカルシンキングではその一歩手前に立ち返ります。
「そもそも“成果”とは何を指すのか?」
「目標の設定そのものがズレていないか?」
「評価される“成果”は誰の基準で決まっているのか?」
問いを掘り下げることで、見えてくる景色がまるで変わります。
表面的な“対症療法”ではなく、
問題の根っこにある構造を見抜くことができるようになるのです。
構造で考える=“考えを見える化”する力
思考を深めるもう一つの鍵が、「構造化」です。
人の頭の中は、感情・情報・直感が入り混じっていて、
放っておくとすぐにごちゃごちゃになります。
そのまま考えても、混乱は深まるばかり。
そこで有効なのが、「関係性で整理する」という発想。
たとえば、
・原因と結果
・目的と手段
・事実と解釈
を区別して整理すると、問題の“位置”がはっきりしてきます。
これを「思考の見える化」と呼び、
自分の考えをチームで共有し、議論の質を上げるための基本としています。
リーダーにとってこれは、
「考えを言語化し、伝わる形にする力」=信頼される力でもあります。
仮説で動くリーダーになる
最後に大切なのは、「仮説思考」です。
完璧な情報が揃うことなど、現場ではほとんどありません。
それでも止まらずに進むために、
今ある情報で“仮の答え”を立て、行動しながら修正する。
これこそが、思考を「実践」に変える力です。
仮説を持つことで、考えながら動けるリーダーになれる。
逆に、仮説を持たずに動くと、
上司の意見や周囲の流れに流されやすくなり、
結果として“思考停止”が再発します。
つまり、クリティカルシンキングとは──
「問いを立て」「構造で整理し」「仮説で動く」ための、思考の筋トレ。
この力が身につくほど、リーダーとしての判断軸が強くなります。
考え続ける姿勢こそが、チームを導く力の源なのです。
第3章:現場で使える思考のステップ──雲→雨→傘思考術
「クリティカルに考えよう」と言われても、
具体的にどうすればいいのか分からない──
そう感じるリーダーは多いと思います。
そんなときに役立つのが、
『コンサル一年目が学ぶこと』でも紹介されている「雲→雨→傘思考術」です。
このフレームは、抽象的な状況を“構造的に考える力”へと変えるシンプルな思考法。
新人リーダーが“考えるリーダー”へ成長するうえで、非常に有効なツールです。
☁️① 雲:状況を正しく捉える(What’s happening?)
最初にすべきは、「いま何が起きているのか」を整理することです。
ここでのポイントは、“感情”や“印象”ではなく、事実を描くこと。
たとえば、
「チームの雰囲気が悪い」
という曖昧な雲を、
「会議で発言が少ない」「雑談が減っている」「報連相が遅れている」
と、観測できる現象に置き換える。
これで“考える土台”が明確になります。
🌧️② 雨:原因を考える(Why is it happening?)
次に、その雲(現象)を生み出している“雨(原因)”を探ります。
ここでクリティカルシンキングが真価を発揮します。
「上司の指示が悪い」「部下のモチベが低い」など、
表面的な答えで終わらせず、多面的に問い直すことが大切です。
たとえば、
- コミュニケーションの機会が減っているのでは?
- チームの目的が共有されていないのでは?
- 成果の基準が曖昧なのでは?
このように「なぜ?」を繰り返し掘り下げることで、
思考の解像度が高まっていきます。
☂️③ 傘:打ち手を考える(What should we do?)
最後に、具体的なアクション=“傘”を設計します。
ここでのコツは、仮説思考を組み合わせること。
「まずは1on1の頻度を週1→週2に増やしてみる」
「会議の冒頭で目的を再確認する」
など、小さく試せる打ち手を仮説として設定し、
実行→検証→修正を繰り返すことで、行動が洗練されていきます。
ポイント:雲・雨・傘を“分けて考える”だけで思考は進化する
多くのリーダーが思考停止に陥るのは、
雲(現象)・雨(原因)・傘(打ち手)を一気に考えてしまうからです。
問題を見つけた瞬間に「じゃあどうする?」と動くのではなく、
一度立ち止まり、段階的に思考を整理する。
これこそが、クリティカルシンキングを現場で使いこなすための第一歩です。
リーダーの役割は、すべてを正しく判断することではなく、
チームとともに考え、前に進むこと。
曖昧な状況に向き合いながらも、問いを立て続ける姿勢こそが、
“思考停止しないリーダー”をつくります。
次章では、この「雲→雨→傘思考術」をどうチームメンバーに伝え、
“考えるチーム”を育てるか──その実践のポイントをまとめていきます。
第4章:考え続けるリーダーがチームを強くする
「考えるリーダー」と「思考停止リーダー」の違いは、
知識量ではなく、姿勢の違いにあります。
前者は、曖昧な状況に出会っても「なぜ?」と問い続ける。
後者は、「誰かの正解」にすがって安心しようとする。
このわずかな差が、時間の経過とともに大きな成果の差を生みます。
チームを強くするのは「一緒に考える文化」
部下が成長するのは、正しい答えを与えられたときではありません。
一緒に「なぜこうなっているのか」「次はどうすべきか」を考えたときです。
リーダーが“考える姿勢”を見せると、
メンバーも「考えていいんだ」と思えるようになります。
そこから生まれるのは、命令で動くチームではなく、思考で動くチーム。
心理的安全性のあるチームとは、まさにこの状態のことです。
正解を探すのではなく、“問いを磨く”
これからの時代に求められるのは、「正解を出す人」ではなく、
問いを立て続けられる人です。
『実践型クリティカルシンキング』の中でも、
思考の出発点として「前提を疑うこと」「問いを深めること」の大切さが語られています。
「なぜそのやり方なのか?」「他の見方はないか?」と自問できる人こそ、
変化の激しい時代に柔軟に対応できるリーダーです。
考え続けるリーダーが生み出す“余白”
考え続けることは、すぐに成果が出るわけではありません。
むしろ、立ち止まる時間が増えるかもしれません。
しかし、その“余白”の中でこそ、チームの本質的な課題や、
一人ひとりの可能性が見えてきます。
「忙しいから考えない」のではなく、
「忙しいからこそ、考える時間を確保する」。
それが、これからのリーダーに求められる姿勢です。
リーダーの仕事とは、
決断し続けることではなく、問い続けること。
そして、その問いをチームと共有しながら、
共に悩み、共に答えを探していくこと。
思考を止めないリーダーがいるチームは、
必ず、変化に強く、しなやかに成長していきます。
まとめメッセージ
「考えることをやめた瞬間、成長も止まる。
考えることを続ける限り、チームも自分も進化し続ける。」
新人リーダーであるあなたが、
今日から“問いを立てること”を始めれば、
その瞬間からチームの未来は少しずつ変わっていきます。


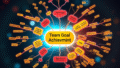
コメント