はじめに:本を読めば読むほど、リーダーとして迷走した日々
新人リーダーに任命された初日、私は大きな不安を抱えていました。「部下をどうマネジメントすればいいのか」「リーダーとして何をすべきなのか」。答えを求めて、仕事帰りに書店へ直行しました。
平積みされたリーダーシップ本、ベストセラーのマネジメント本、カリスマ経営者の自伝。「これを読めば何とかなるはずだ」と、片っ端から購入しました。毎晩遅くまで読み漁り、翌日には本に書かれていたことを実践する。そんな日々を繰り返していました。
しかし、結果は散々でした。今日は「ビジョンを語れ」と書いてあった本の通りに熱く語り、翌日は「傾聴が大切」と書いてあった本を読んで部下の話をひたすら聞く。右往左往する私に、部下たちは明らかに困惑していました。「課長、結局どうしたいんですか?」と聞かれたときの気まずさは、今でも忘れられません。
時間とお金を無駄にし、むしろ部下との関係も悪化させてしまった私は、ある日気づきました。「問題は本ではなく、本の選び方と使い方だったのだ」と。
読まなくていい本の3つの特徴
100冊以上のリーダー本を読んで失敗を重ねた結果、私は「読まなくていい本」には明確な特徴があることに気づきました。
特徴①:カリスマ創業者の成功体験だけが書かれた本
「私は〇〇で年商100億円企業を築いた」「私のリーダーシップ論」といったタイトルの本です。確かに読み物としては面白いのですが、新人リーダーにとっては再現性が低すぎます。
著名な経営者の本を読んで「朝5時に起きて瞑想する」「常に攻めの姿勢で」といったアドバイスを真に受け、実践しようとしましたが、そもそも環境も立場も全く違います。創業者とサラリーマンの新人リーダーでは、持っている権限も背負っているものも異なります。
成功体験は確かに学びになりますが、それはあくまで「その人の、その環境での」成功に過ぎません。新人リーダーに必要なのは、再現可能な具体的手法なのです。
特徴②:抽象的で具体的なアクションがない本
「信頼関係を築くことが大切です」「ビジョンを示しましょう」「部下のモチベーションを高めましょう」。確かに正しいことが書いてあります。しかし、「で、具体的にどうすればいいの?」という疑問には答えてくれません。
新人リーダーが知りたいのは「what(何をすべきか)」ではなく、「how(どうやってやるのか)」です。明日の1on1で使える質問フレーズ、会議で意見を引き出す具体的な進行方法、部下を注意するときの言葉の選び方。そういった実践的な内容がない本は、読んだ瞬間は「なるほど」と思っても、翌日には何も変わっていません。
特徴③:完璧なリーダー像を求める理想論の本
「リーダーは常に冷静であるべき」「リーダーは決断力がなければならない」「リーダーは部下全員から信頼されるべき」。理想のリーダー像がこれでもかと並べられている本です。
こうした本を読むと、最初は「そうだ、こうならなければ」と意気込みます。しかし現実には、感情的になることもあるし、迷うこともあるし、部下全員に好かれるなんて不可能です。理想と現実のギャップに苦しみ、「自分にはリーダーの素質がないのかもしれない」と自信を失ってしまいます。
新人リーダーに必要なのは、完璧なリーダーを目指すことではありません。不完全な自分を受け入れながら、少しずつ成長していく道筋なのです。
失敗から学んだ、本当に大切なこと
数多くの失敗を経て、私はようやく気づきました。本を読む前に、まず「自分がどうしたいのか」を考えるべきだったのです。
本の内容を全部鵜呑みにして、片っ端から試していた私。しかし、すんなり腑に落ちて読み進められる本もあれば、著者の意見が全て自分の考え方に合わない本もありました。結局、本にも「合う、合わない」があるのです。
それは当然のことでした。なぜなら、著者と私は違う人間だからです。大切なのは、自分がどんなリーダーになりたいのか、どんなチームを作りたいのかを明確にすること。その軸があって初めて、自分に合う本を選ぶことができます。
なんでもかんでも読めばいいわけではありません。自分がどう思ったのか、どうしたいのかが大事なのです。本はあくまでヒントを与えてくれるもの。最終的に判断し、行動するのは自分自身です。
この気づきを得てから、私の本選びは変わりました。そして、本当に自分を成長させてくれる本と出会うことができたのです。
実際に私を救った3冊
ここからは、新人リーダー時代の私を本当に救ってくれた3冊をご紹介します。いずれも、先ほど挙げた「読まなくていい本」の特徴とは真逆の本です。ここに載っている本以外は読まなくていい訳ではないので誤解のないように!
1冊目:『成長マインドセット』吉田行宏
この本に出会ったのは、リーダーになって3ヶ月目、完全に自信を失っていた時期でした。スキルを学んでも、研修を受けても、なぜかうまくいかない。「自分には才能がないのだろうか」と悩んでいたとき、この本が「成長の本質」を教えてくれました。
本書の核心は「アイスバーグ理論」です。氷山の見える部分(成果)は全体のわずか10%に過ぎず、水面下には能力・スキル、ふるまい・習慣・行動、意識・想い、人生哲学といった目に見えない部分が積み重なっている。成長とは、この氷山全体を大きくすることだという考え方です。
この理論で、私はようやく自分の問題に気づきました。私はスキルばかり学んでいて、その土台となる「習慣」や「意識」を変えていなかったのです。1on1のテクニックを学んでも、「部下の話を聞く習慣」がなければ意味がない。戦略を学んでも、「チームを信じる想い」がなければ実行できない。
さらに本書は、成長を阻害する「2つのブレーキ」と、成長を促進する「2つのアクセル」を具体的に解説してくれます。特に「悩みブレーキ」の章は、悩むことで行動が止まっていた自分に気づかせてくれました。
完璧なリーダーを目指す必要はない。アイスバーグをバランスよく、少しずつ大きくしていけばいい。そう思えたことで、肩の力が抜け、むしろ部下との関係も良くなりました。
2冊目:『嫌われる勇気』岸見一郎・古賀史健
「部下全員に好かれたい」「嫌われるのが怖い」。そんな思いが強すぎて、優柔不断になっていた私に、この本は重要な視点を与えてくれました。
アドラー心理学をベースにした本書は、対人関係の悩みの本質を突いています。「他者の課題と自分の課題を切り分ける」という考え方は、特にリーダーとして必要な境界線を教えてくれました。
部下がどう思うかは部下の課題であり、私がコントロールできることではない。私ができるのは、誠実にリーダーとしての責任を果たすことだけ。この割り切りは、冷たいようで実は健全な関係性を築くための土台になりました。
もちろん、部下を無視していいという意味ではありません。しかし、「嫌われたくない」という恐怖から下す判断は、結局誰のためにもならないのです。正しいと思うことを、勇気を持って実行する。その姿勢が、むしろ部下からの信頼につながることを、この本は教えてくれました。
3冊目:『エッセンシャル思考』グレッグ・マキューン
リーダーになって一番苦しんだのは、「全部やらなければならない」というプレッシャーでした。部下の相談、会議、報告書、戦略立案。すべてを完璧にこなそうとして、結果的にどれも中途半端になっていました。
この本は、「より少なく、しかしより良く」という哲学を教えてくれました。すべてに対応するのではなく、本当に重要なことを見極めて、そこに全力を注ぐ。この考え方は、新人リーダーにこそ必要なものです。
特に実践的だったのは、「90点ルール」です。選択肢を評価するとき、100点満点で90点未満なら断る。この明確な基準があることで、優先順位をつけやすくなりました。
また、「ノーと言う技術」のセクションは、何度も読み返しました。断ることは冷たいことではなく、本当に大切なことを守るための選択です。この本を読んでから、会議の数を減らし、部下との1on1に時間を割くようにしました。すると、チームの生産性も向上し、私自身の余裕も生まれました。
すべてを頑張るのではなく、何を頑張るかを選ぶ。この思考法は、リーダーとしてだけでなく、人生全体においても大きな影響を与えてくれました。
まとめ:本選びで大切なこと
新人リーダーの皆さんにお伝えしたいのは、「有名だから」「売れているから」という理由だけで本を選ばないでほしいということです。
まず、自分がどんなリーダーになりたいのか、今どんな課題に直面しているのかを明確にしてください。その上で、自分の価値観や状況に合った本を選ぶのです。
そして、10冊を流し読みするよりも、1冊を深く読み、実践することの方がはるかに価値があります。本を読むこと自体が目的ではありません。本から得た学びを、実際の行動に変えることが大切なのです。
今回ご紹介した3冊は、あくまで私に合っていた本です。あなたにとってのベストな1冊は、また別のものかもしれません。しかし、「自分はどうしたいのか」という軸を持って本を選べば、必ずあなたのリーダー人生を変える1冊に出会えるはずです。
リーダーとしての旅は、決して平坦ではありません。しかし、適切な本との出会いは、その旅を支えてくれる心強い道しるべになります。あなたにとっての「運命の1冊」が見つかることを、心から願っています。
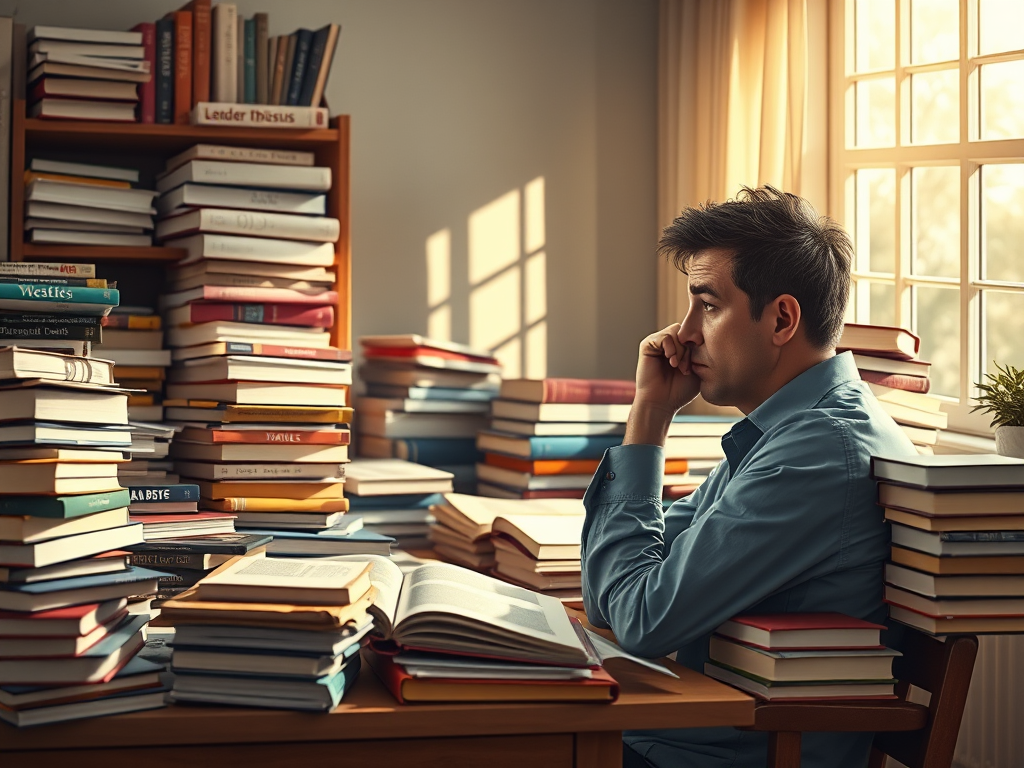

コメント